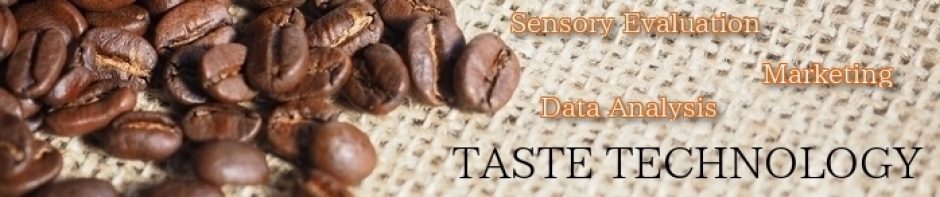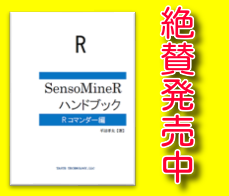官能評価では、5点法や9点法などの多段階スケールやラインスケール(またはビジュアルアナログスケール:VAS)などの独立評価型スケールが主流です。
順位法は「ちょっと古くて、情報量が少ない、論文で目新しさがない」など積極的に使われることが少なくなりました。
官能評価において順位法は、試料の差異や類似を明らかにするためのデータ取得の目的でも使われますが、前段階の試料スクリーニングやパネルトレーニングで使われることも多いです。
順位法は、被験者が複数試料(3つ以上)を試用して、指定された属性について順に並べた順位データを取得する手法です。一度に尋ねる属性は1つだけであり、「甘さの強い順番」「苦味の強い順番」「好ましい順番」などのように特定の1属性について回答者の認知に基づいて試料を並べます(または、順位を回答します)。
順位法についてのISO規格は、ISO8587(2006)が発行されています。2006年が最新版なのですが、2013年に補足版が公開されています。
※弊社ではこの補足版も購入しているのですが、あまりのページ数の少なさに驚きました(この改訂規模なら正誤表で対応してほしいですね)。
さて、順位法から得られるのが「順位データ」ですが、AIや機械学習の分野では「順位データ」の価値が再評価されています。検索エンジンのリザルトページやECサイトのレコメンド、音楽ストリーミングのプレイリストの最適化など、Web業界の最先端アルゴリズムは順位データを核にしています。
最先端技術でも活躍中の「順位データ」ですが、官能評価でも下記の様なメリットがあります。
●直感的な操作で被験者負担が小さい
●個人別の点数の付け方の差が出にくい
●訓練の有無や文化の違いの影響が出にくい
●大量収集との相性が良い
これらの利点が認識されて「順位法」が再び脚光を浴びています。
「順位法」を単体で使うというよりは、評価の前段階で使ったり、精度より簡便性を重視したり、AIの学習データ用に規模の大きなデータが求められる調査では今後更に重要な手法となってくるでしょう。
企業実務では、評点データから急に順位データに変更するのは難しいと思います。しかし、スクリーニングやトレーニングなどの前段階であれば比較的導入しやすいでしょう。
AI導入の準備をされている方、パネルトレーニングやスクリーニングの省力化を検討されている方は、「順位法」の利用をお勧めします。
今回は、クラシックだけど最先端「順位法」についてご紹介しました。