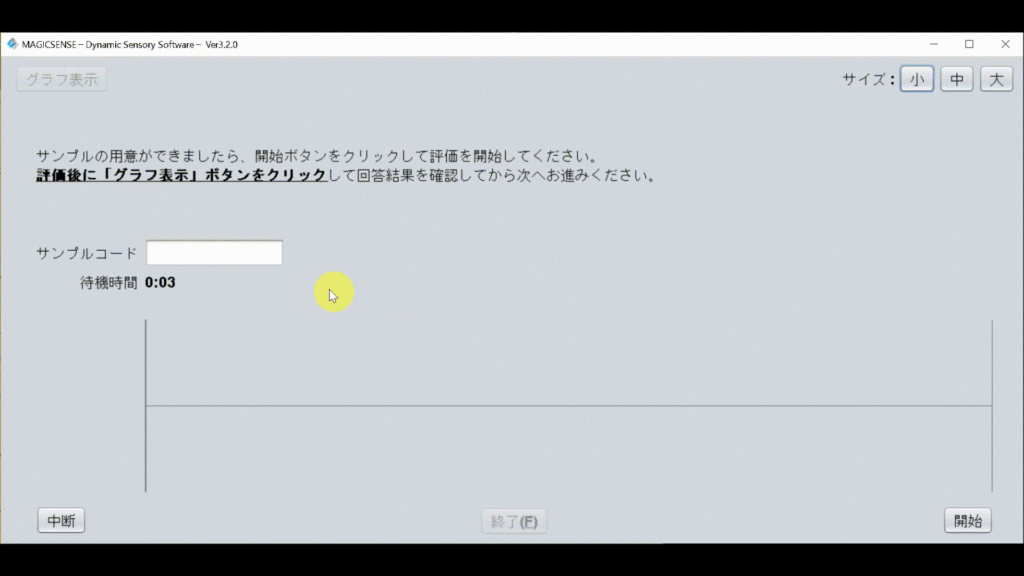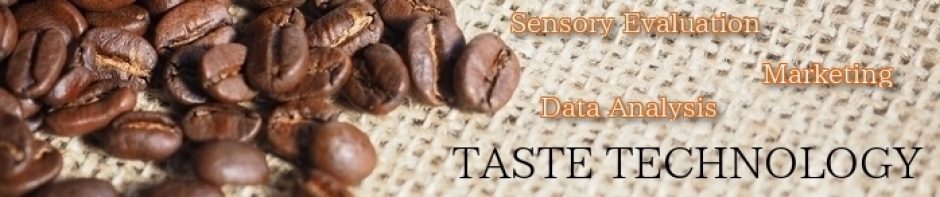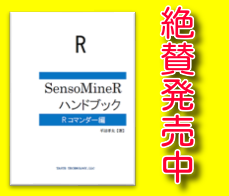今年も残すところあと数日となりました。
2023年はChatGPTと生成AIなどのAI躍進で始まりました。
そんな今年2023年の官能評価関連の状況を振り返りたいと思います。
1.ChatGPTと生成AI
2.ISO・JIS関連の更新情報
1.ChatGPTと生成AI
2022年11月にChatGPTのサービスが開始されてから1年が経ちました。
生成AI関連ではまさに怒涛の1年でした。
技術的な話で言えば順当な進歩なのですが、ChatGPTのサービス提供によって一般人にサービスが大きく広がりを見せたのが大きなポイントでしょう。
また、これにより各AIの競争と投資が進み、非常に大きなうねりとなっています。
今年開催されたPangbornでも多くのAI関連の講演がありました。
弊社でもChatGPTに関する無料オンラインセミナーを3回開催いたしました(動画は販売中です)。
実際、私自身もChatGPTを使ってみて、官能評価のいくつかタスクでは十分に使えるレベルにあると感じております。
特に下記2点は実際に使用しているタスクです。
a.データ解析用のコード生成
b.論文や情報の要約
a.データ解析用のコード生成
都度のデータ解析(アドホックな解析)は使い慣れた統計ソフトで解析した方が早いのですが、繰り返し同じ作業のデータ解析の場合は必要に応じてプログラムの作成をしておりました。
このプログラムコード(R, Python)を作成をChatGPTに依頼して書いてもらっています。
非常に早く、簡単にできるようになりました。
b.論文や情報の要約
論文やテキストがPDFなどで入手できますが、これを読み込んで理解するのはそれなりに時間がかかります。
また、今年のPangbornの動画の内容を把握するためには動画を見る必要がありました。
PDFでは、ChatGPTに読み込ませて要約をしてもらいます。
動画の場合は色々な方法がありますが、私は動画を音声ファイル(MP3)に変換して、OpenAIのwhisperで文字起こしをしてからChatGPTで要約をしてもらいます。
どちらも情報の正確性は自分で確認する必要がありますが、コストパフォーマンスが非常に高いです。
また、ハルシネーションなどの誤った回答の生成についても大分削減されてきており、近い将来にはかなり高い精度で利用できそうです。
これらの話をお客様としますが、多くの企業では企業内でのChatGPT等のサービス利用に至っていないようです。
しかし、皆さん思い出してください。
今や将棋や囲碁、チェスはAIの独壇場です。以前はこれらの分野で機械(AI)が人間に勝つのは無理だと言われてきていましたが、気が付いたら人間が勝てなくなってしまいました。
ChatGPTなどのLLM(大規模言語モデル)以外にも画像や動画、音楽の生成AIが高い性能で提供されてきています。
引き続き技術的な進歩は間違いなく進みますが、著作権や生成されたモノの利用の仕方などの制度面によっては多少のブレーキもかかるとは思います。
しかし、生成AIの進化の流れは来年も続くことでしょう。
2.ISO・JIS関連の更新情報
2023年のISO更新情報です。
今年は規格更新が5つ発行されました。新規規格の発行はありませんでした。
Standard
ISO 22935-1:2023(<-2009)
Milk and milk products – Sensory analysis – Part 1: Recruitment, selection, training and monitoring of assessors
Publication date : 2023-04
Edition : 2
Number of pages : 17
Standard
ISO 22935-2:2023(<-2009)
Milk and milk products – Sensory analysis – Part 2: Methods for sensory evaluation
Publication date : 2023-04
Edition : 2
Number of pages : 23
Standard
ISO 22935-3:2023(<-2009)
Milk and milk products – Sensory analysis – Part 3: Method for evaluation of compliance with product specifications for sensory properties by scoring
Publication date : 2023-04
Edition : 2
Number of pages : 7
Standard
ISO 16657:2023(<-2006)
Sensory analysis – Apparatus – Olive oil tasting glass
Publication date : 2023-06
Edition : 2
Number of pages : 5
Standard
ISO 8586:2023(<-2012)
Sensory analysis – Selection and training of sensory assessors
Publication date : 2023-04
Edition : 2
Number of pages : 38
今年はChatGPTなどの生成AI系サービスの展開に驚いた1年でした。
実際、弊社のサービスも見直しが必要となってきております。
今すぐ官能評価がなくなるという訳ではありませんし、逆にAI化が進むほど感覚情報の数値化が求められてくると考えています。
2024年も時代の変化に対応しながら、頑張っていきたいと思います。
本年も大変お世話になりました。
来年も何卒宜しくお願い致します。