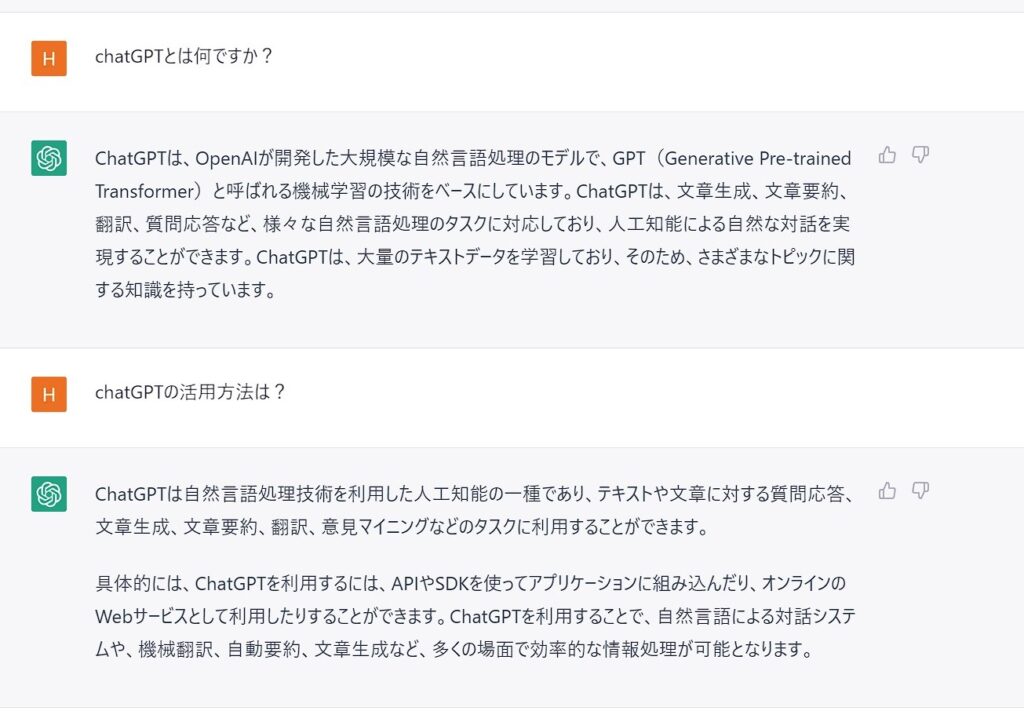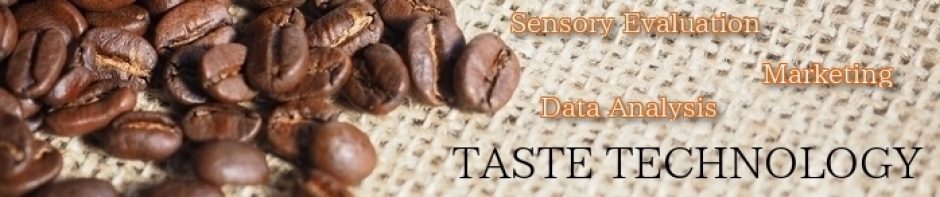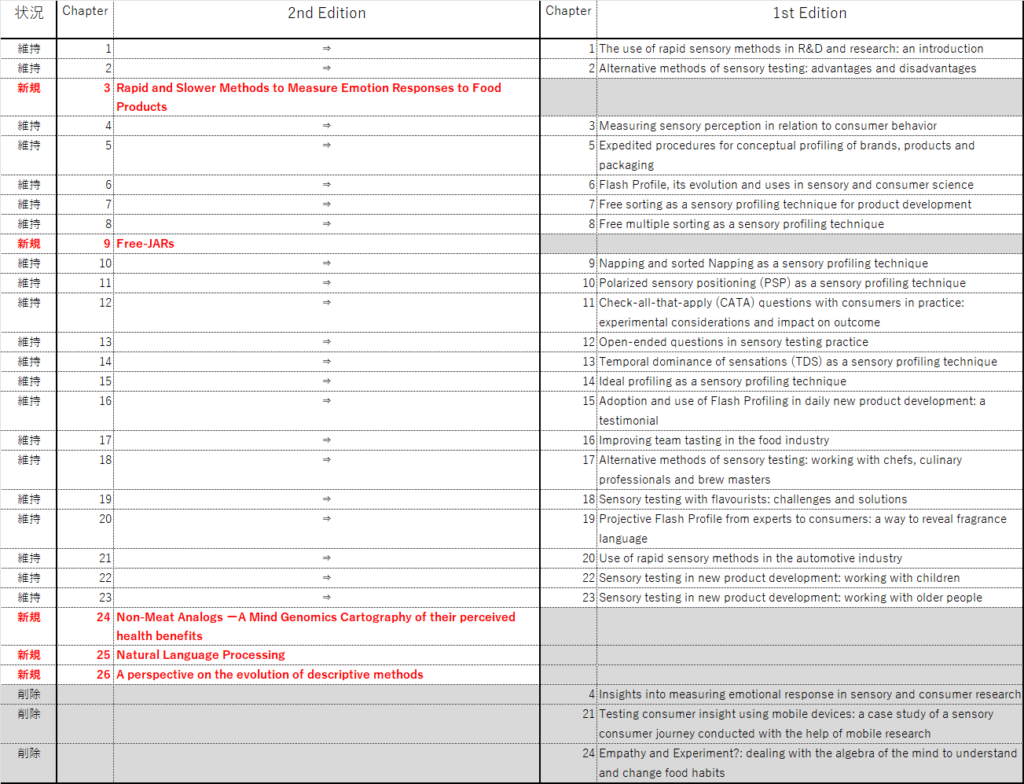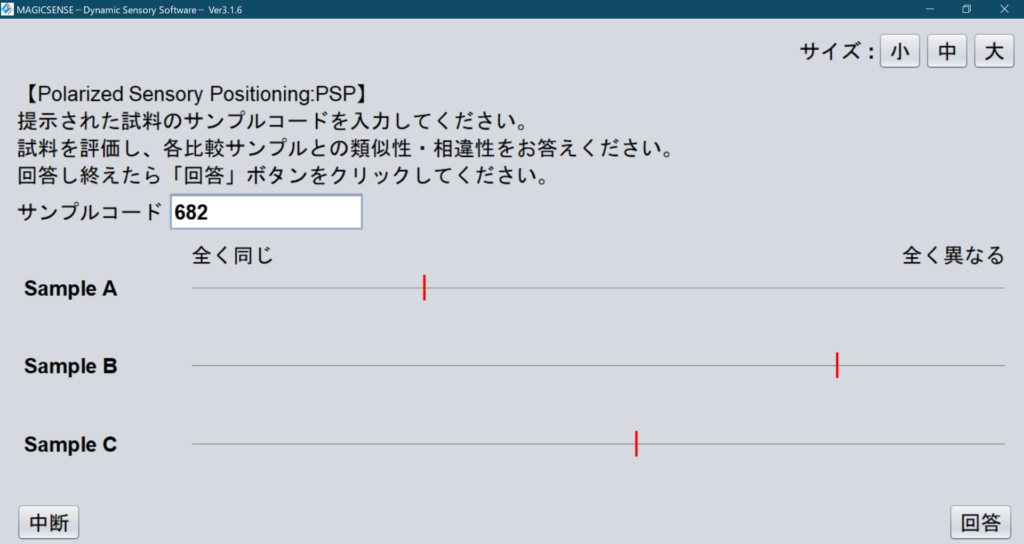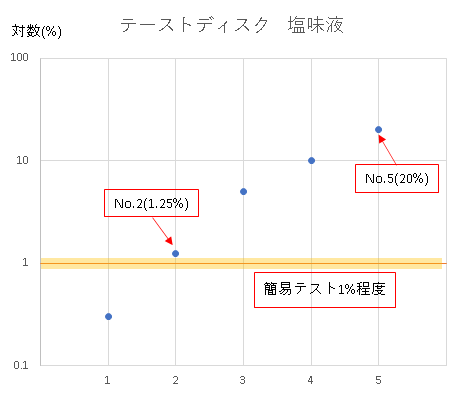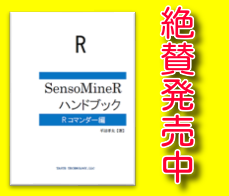今年も残すところあと数日となりました。
2021年も激動の一年でした。新型コロナの感染拡大により生活様式が大きく変化した社会の中で東京五輪の開催されました。新型コロナウィルスの変種が次々と現れて、なかなか収束の目処が立っていないように思えます。
このブログを書いていたら、今度は東京23区を震源とする地震までありました。東京23区を震源とする地震は珍しいですね。
今年2021年の官能評価関連の状況を振り返りたいと思います。
1.Pangborn2021のオンライン開催
2.ISO・JIS関連の更新情報
1.Pangborn2021のオンライン開催
今年開催されたPangbornシンポジウムはオンライン開催となりました。カナダのバンクーバー開催の予定でしたがオンライン開催に変更になりました。
個人的にはオンライン開催になって便利になったと感じています。
便利だった理由は2つあります。
1つ目は動画が録画されて一定期間公開されたことです。これによって見逃したり、何度も見たい内容を確実に見ることができるようになりました。会場開催の場合は、複数の場所で同時開催されることがありますので見逃しが出てきます。また、英語のプレゼンテーションに理解が追いつかない時は動画であれば見直すことができます。さらに動画ならばgoogle翻訳や字幕機能を使って理解しやすくなります。
2つ目は、開催地への移動が無いことです。当たり前ですが、オンラインなので自宅や会社など好きな場所で参加することができました。Pangbornは8月頃に開催されているのですが、いつも仕事の都合で参加できないことがほとんどでした。シンポジウム自体が3,4日間とこれに前後の移動日を含めると1週間近く時間を取られてしまいます。オンラインでも時間の拘束はありますが、最小限に抑えられているというのがメリットです。
一方でデメリットもありました。私の感じたデメリットを2つあげます。
1つ目は、他の参加者とのコミュニケーションが取りにくかったことです。
顔を合わせてシンポジウムに参加していれば、何かしらのきっかけで会話することがあります。それに食事や休憩時間など主催者側もコミュニケーションの機会を作っています。
今回、ブラウザやアプリ上で参加者間のコミュニケーションツールも提供されていましたが、私は結局知っている人にしか使いませんでした。やはり初めて会った人にオンラインでいきなり話しかけるのは気が引けます。実際に会場で会っていれば「どこから来ましたか?」なんて会話も始められるのでしょうが、オンライン直メッセージはハードルが高かったです。
これはオンラインコミュニケーションの慣れの違いもあるのかもしれませんので、有効活用された方もいると思います。
2つ目のデメリットは、配信トラブルです。
今回のPangbornでは初日からトラブルが発生しました。トラブルの原因は主催者側のネットワークや配信ツールが問題の場合もありますし、利用者側のネットワークが問題となる場合もあります。他のオンラインシンポジウムでも発生していますが、オンライン会議・セミナー等の経験値が上がってくればトラブルは減ってくると思いますが、当面はこの問題がオンライン開催のデメリットでしょう。
次回2023年はフランス・ナント(Nantes,France)に決定しています。
会場開催に加えてオンライン配信もやっていただければ両方のメリットを享受できるのですが、会場参加者が減ってしまうかもしれないのでバランスが難しいですね。
フランス・ナントでは新型コロナが落ち着き、会場開催ができることを願っております。
2.ISO・JIS関連の更新情報
2021年のISO更新情報です。
今年は更新3、新規2の合わせて5つの規格が発行されました。
比較的多かったと思います。
特に興味深いのはISO 20784「官能及び消費者製品の主張の実証に関するガイダンス」です。
ちょっとわかりにくいタイトルですが、商品の広告やパッケージに記載する感覚的な内容(おいしい!、息爽やか!など)をデータで実証するためのガイドラインです。
医薬品であれば様々な法的規制がありますが、一般的な消費者向け商品では感覚的な主張(最高にいい匂い!)の規制は業界ごとにバラバラです。
結局の所、その商品を発売する国や地域の規制に従うしか無いのですが、どのように感覚的な主張をサポートする実証研究を行うかの一般的なガイドラインがISO 20784には示されています。
おすすめしたいのはAnnex Aケーススタディです。
なんと8つのケース(事例)が掲載されています。
A.1 Non-comparative- Affective:“Tastes great”
A.2 Non-comparative- Performance:“Leaves no residue”
A.3 Non-comparative- Performance:“Easy to prepare”
A.4 Comparative- Affective:
“30 % reduced salt, same great taste”
A.5 Comparative- Unsurpassed – Performance:
“Cleans as well as the leading brand”
A.6 Comparative- Superiority – Affective:
“The ketchup taste consumers prefer on their burger”
A.7 Comparative – Superiority – Performance:
“Less clumping than other comparably-priced brands”
A.8 Non-comparative – Attribute:
“Now less bitter” or “now with more roasted flavour”
例えばA.1はサラダドレッシングの事例です。
パッケージラベルに「Tastes great」(すごくおいしい)を表示したい時にどんなテストを実施するかが取り上げられています。
テレビやインターネット広告だけではなく、商品コンセプトやパッケージに記載する言葉を扱う業務の方は目を通しておくと良いと思います。
ISO購入するほどではないという方は、こちらのPDFを参照しても良いでしょう。ISO20784の巻末Bibliographyにも掲載されています。
ISO 20784が官能評価分野で発行されたことは興味深いです。
官能評価技術者は、研究室にこもって商品のプロファイルや品質チェックをしているだけではなく、パッケージや広告といった他部門との協業が欠かせなくなってきているためだと考えています。
この他、ISO4120三点試験法やISO11056マグニチュード推定法は、定番の官能評価手法をアップデートしたものです。
特筆すべきはISO 11056マグニチュード推定法にて、パネリスト因子(assessor factor)が固定因子だけだったのですが、ランダム因子としても扱うようになりました。ISO 11132でもモデルの拡張がされています。多くの官能評価ソフトウェアでは対応していましたが、ISO規格の方もパネリスト因子をランダム因子として扱う方向になりました。
ISO 22308は新規の規格ですが、コルク樹皮の利用者に特化した規格です。
以下、2021年に発行された規格一覧(規格番号順)です。ISOの「sensory」検索結果はこちら(ISO.org)
【更新】
●ISO 4120:2021
官能試験-方法論-三点試験法
Sensory analysis — Methodology — Triangle test
ページ数:17p
発行年月日: 2021-03-03
主な変更点:
・食品および飲料の用途を超えて一般化されています。
・以前に強調された推測モデルに加えて、サーストニアンモデルの使用方法に関するガイダンスが追加されました。
●ISO 11056:2021
官能分析-方法-マグニチュード推定法
Sensory analysis — Methodology — Magnitude estimation method
ページ数:31p
発行年月日: 2021-05-27
主な変更点:
・パネリスト因子は固定因子またはランダム因子と見なされます(以前の版では、パネリスト因子は常に固定因子と見なされていました)。
・さまざまなテーブルを取得するために使用されるRコマンドが明示的に指定されています(以前のエディションでは、結果のテーブルのみが指定されていました)。
・数値例は、ユーザーがテーブルの処理の進化を理解できるように、変更なしで保持されています。
・新しい例がB.2として追加されました。
●ISO 11132:2021
官能試験-方法論-定量的記述感覚パネルの性能測定のためのガイドライン
Sensory analysis — Methodology — Guidelines for the measurement of the performance of a quantitative descriptive sensory panel
ページ数:22p
発行年月日: 2021-09-08
主な変更点:
・タイトルが変更され、ドキュメントが記述型パネルに適用できることを明示しました。
・スコープが改訂されました。
・定義が改訂され、新しい用語エントリが追加されました。
・専用手順のプロセスが改善されました。
・実験計画がレビューされ、拡張されました。
・分散分析に関連する統計分析は、特にセッションとパネリスト(固定またはランダム)の効果と相互作用に関して、より多くのモデルを含むようにレビューおよび拡張されています。
・スコープの変更に合わせて、再現性に関連する副次句(具体的には元の6.4.4および7.4)と付録BおよびCが削除されました。
【新規】
●ISO 20784:2021(新規)
官能分析-官能及び消費者製品の主張の実証に関するガイダンス
Sensory analysis — Guidance on substantiation for sensory and consumer product claims
ページ数:18p
発行年月日: 2021-03-23
●ISO 22308-1:2021(新規)
瓶詰め製品として選択されたコルク樹皮-第1部:官能評価-浸漬による官能評価の方法論
Cork bark selected as bottling product — Part 1: Sensory evaluation — Methodology for sensory evaluation by soaking
ページ数:7p
発行年月日: 2021-01-07
以上、2021年のISO発行状況をご紹介しました。
ISOの傾向としてRの引用が増えてきています。実務でもRの利用が増えてきていますので、現実に即したものでしょう。また、解析手法もソフトウェア等で採用されて普及されてきているアプローチが採用されており、妥当といえます。規格ですので進歩的なものは採用されにくいのでしょうが、ある程度普及されたところで反映されていると思います。
しかし、日本の実務レベルとしてはISOの内容でさえ進歩的とも言えてしまうのが何とも歯がゆいですが・・・。
最後に
2021年は、2020年よりは業務が進められたと思います。
しかし、コロナ以前と同じ方法では実施できない調査や官能評価もあり、例えばオンライン官能評価やオンライン・パネルトレーニングなど様々なアプローチを提案・実行してきました。
新規データが取れなくて困っている企業様には、既存のデータを使ったプロファイル推定など、データマイニング・機械学習などの応用も行ってきました。社内パネルの活動が少なかったクライアントも多かったですが、過去の評価データを使ったパネルパフォーマンスのチェックが出来てちょうど良かったと思います。
今年もあと僅かとなりました。
皆様、良いお年をお迎えください。